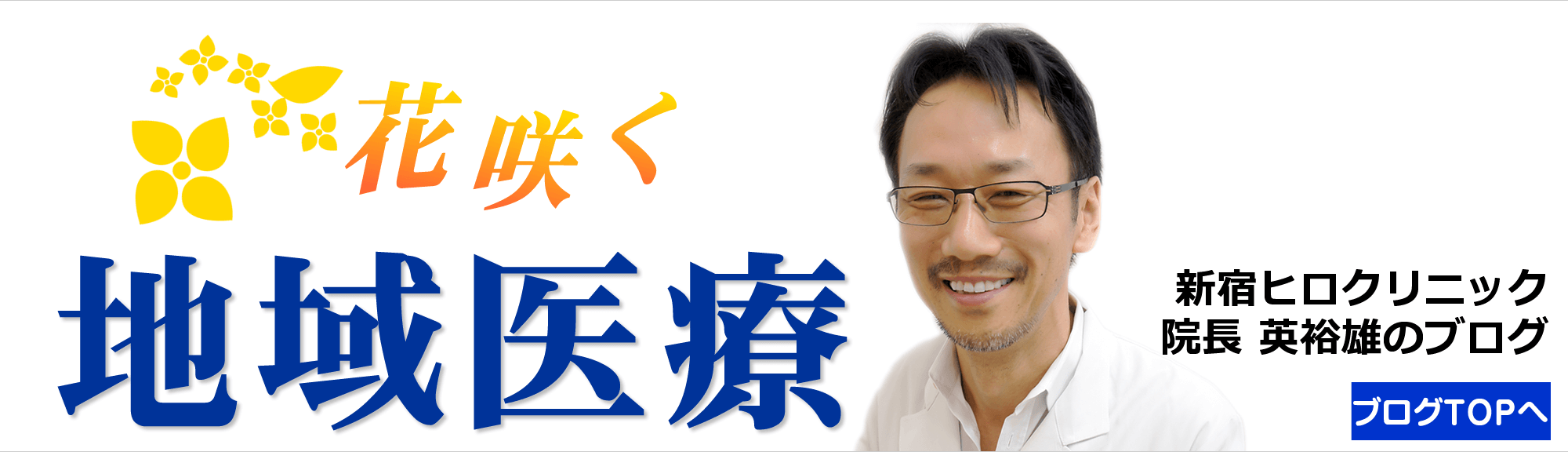在宅医療に従事する医療者が増えている。昨今では日本在宅医学会での研修プログラムの充実など研修や教育の機会も増えてきた。しかしまだまだ在宅医療における臨床研究は少ないままである。
在宅医療現場では、臨床的疑問は生じないのだろうか?いや在宅現場には限りなくたくさんの臨床的疑問がわいてくる。
例えば、各在宅医療機器の在宅ならではの管理はどうすべきか?寝たきりの高齢者にどこまでの血圧管理が好ましいのか?悪性腫瘍患者の予後予測評価は果たして在宅で成り立っているのだろうか?などなど無限ともいえる臨床的疑問が広がっている。
つまり在宅医療は臨床研究の宝庫であるといえる。しかし実際にはそれがまったく進んでいない。
昨日当院では、東京大学在宅医療学拠点の山中崇先生に「在宅における研究の在り方について」についてご講演いただいた。
まだまだ進んでいないが、今後、東大や日本在宅医学会を中心に少しずつ条件整備しいくとのことだった。
では研究するには、どのような課題があるのだろうか?
1・臨床的疑問を明確にする。
2・先行研究や文献などを調べる。
3・実際の研究デザインをする。
4・倫理委員会などによる研究の妥当性、適正性などの評価を受ける。
5・実際の臨床研究を行う。
6・統計的解析を含めて、結果の妥当性を検証する。
7・論文にまとめたり、学会に発表する。
ちょっと考えただけで、このような膨大なプロセスがある。
しかしだからと言って人任せでいいわけではない。
これまで長いこと在宅医療を行ってきた者の一人として、少しずつでも、研究的素地を整備していきたいと感じている。
千里の道も一歩よりである。