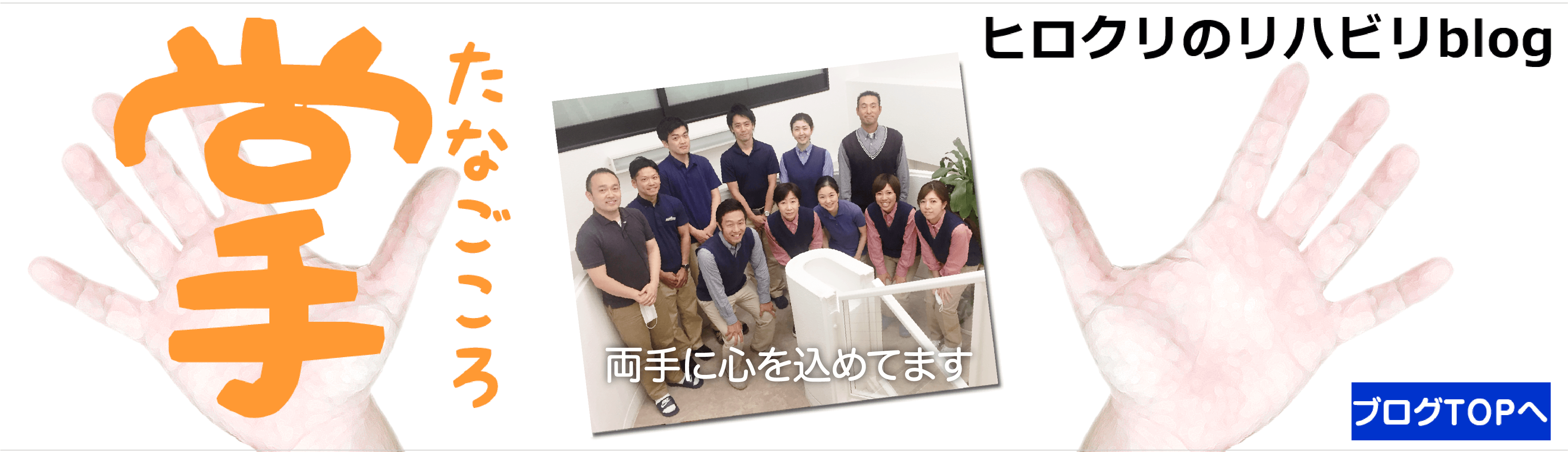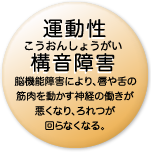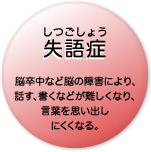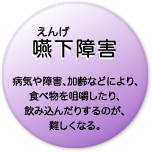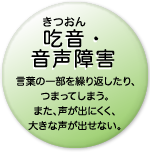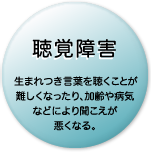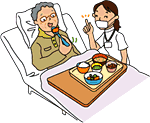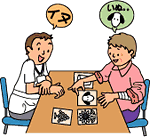言語聴覚士(ST)は、病気や交通事故などの後遺症による、失語症や高次脳機能障害、構音障害といった、ことばや聞こえなどのコミュニケーションにお悩みの方や、食べ物を食べる、飲み込むといった摂食・嚥下に問題をお持ちの方に対し、専門的な検査および評価を実施し、心身機能の回復・維持を図るリハビリを行う専門職です。
訪問STは、STによるリハりビリを受けたくても通院ができない、近隣に専門施設がないといった方や、ことばが思うように話すことができない為に外に出ることが苦手である、摂食・嚥下障害の為、ご自宅のお食事に困っているといった方へ、セラピストがご自宅へお伺いし、ご本人、ご家族のご希望に沿ったリハビリプランを立案し、必要に応じ、検査・治療・支援・援助をご自宅で行います。
実際の生活場面でリハビリテーションを実施するため、ご本人にとって身近なものや興味関心のあるものを使用して言語訓練を行ったり、あるいは日常的な困りごとについて具体的な援助方法をご家族に提案したりといったことが可能です。
訪問STはまだまだ数が少なく、また認知度も高いとは言えない状況があります。
今後ブログを通して訪問STのリハビリについて少しづつご紹介していきたいと思います。