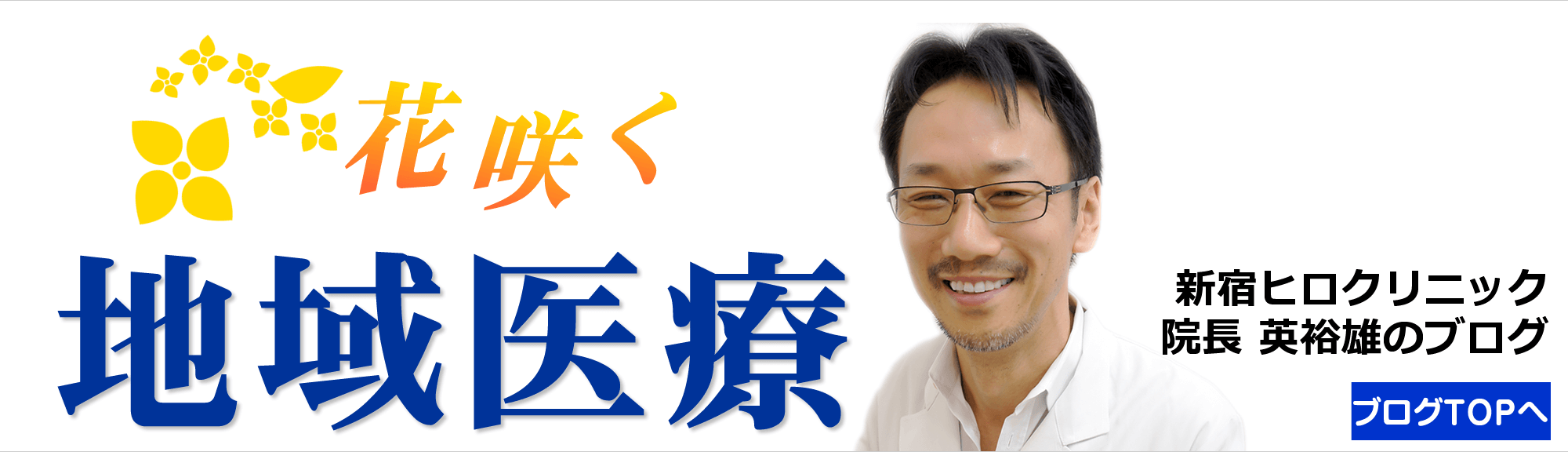昨日、懐かしい人々に合うことができた。
自分が若い時にお世話になった方々だ。
私は研修医を浦和で過ごした。
その当時、私に目をかけてくださった方々だ。
その浦和で開かれる講演会で、私に在宅医療の話をと声かけてくださったのは、ハーモニークリニックの中根晴幸理事長。中根先生は私にとって生涯の恩人でもある。当時右も左もわからない一介の研修医だった私を在宅医療の道にいざなってくれたのは中根先生だったからだ。
「英君。これからは在宅医療の時代になるんだよ。」そんなことを中根先生は何度も研修医の私に言ってきかした。在宅医療って何?という感じでちんぷんかんぷんだったが、何となくそんな気もすると私も思えた。
そんな中根先生に、浦和で在宅医療の講演をするようにと言われたとき、申し訳ない気持ちと、少しでも恩返しできたらと思う気持ちで、講演会に臨ませていただいた。
昨日の講演会では私はほとんど在宅医療の医療的側面はお話しせずに、業務的側面についてお話しした。
最近外来を始めてみると、改めて在宅医療は様々な業務の集約が重要であるということに気づかされる。
その業務をこなす能力こそが、在宅医療の大きな柱になる。
24時間365日対応する業務。ケアマネジャーや地域の方々と連携をとるという業務・・・これら様々な業務の確立があって初めて、熱意や情熱のある在宅医療ができるという風に思えるからだ。
今日の私の講演が、少しでも御恩返しになったかどうかはわからない。
でも私の原点である。医療の故郷に触れることができて、楽しいひと時だったことは確かだ。
様々な昔の情景がフラッシュバックしてきた。懐かしいひと時だった。