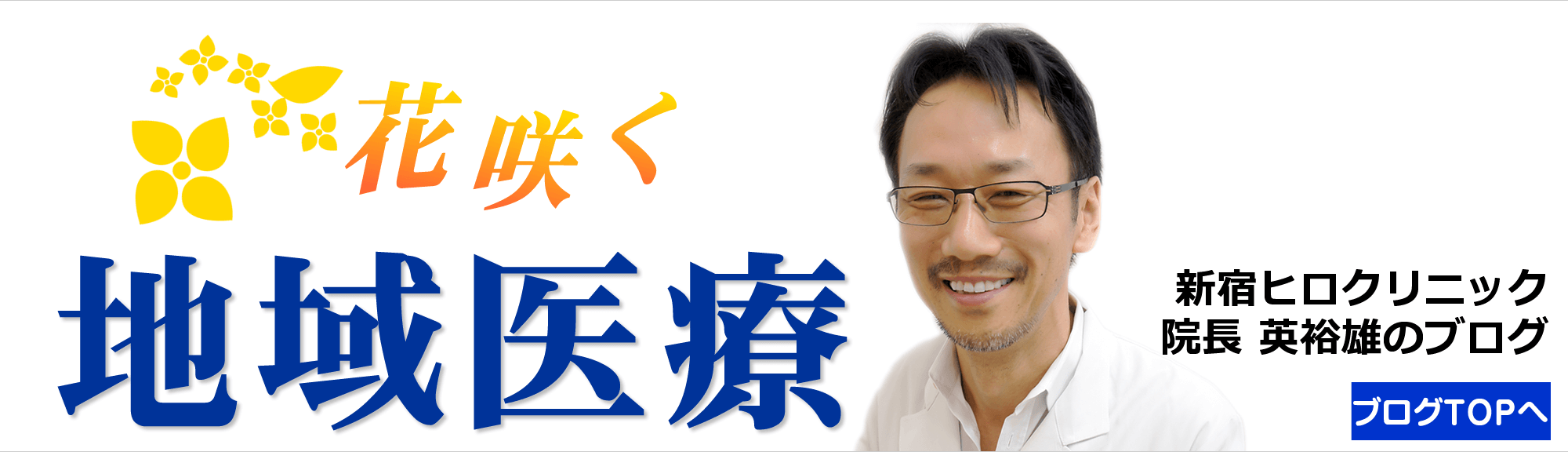訪問診療の現場で発熱された患者さんの治療を行うことは珍しくない。通常は対症的対応。つまり解熱剤を使う。水分補給を行う。床ずれや肺炎などの合併症を防ぐ。などしながら自然回復を待つことが多い。
この上で、発熱の理由として細菌感染を疑う。もしくは心配する場合に抗生剤使用をすることも少なくない。
しかしこの抗生剤使用が難しい。投与ルートの問題、投与回数の問題、さらに適切な抗菌薬選択や効果判定などの問題が、からんでくるからだ。
在宅の患者さんは超高齢であり、多くの合併疾患合併障害を患っていらっしゃること。さらに発熱時には、普段の状況に比べてさらに悪化していることが多いので、普段口から薬が飲める方でも、その時には飲めなくなっていたりする。
したがって、元気があり薬が飲める場合には経口抗菌薬を使えるが、飲めそうもない時には注射の抗菌薬を使用することとなる。
そして注射薬の場合には、どうしても一日複数回の医療者訪問が難しいので、どうしても投与回数の少なく、短時間投与が可能な抗菌薬が好まれる傾向がある。
起因菌の検索のための培養検査は在宅でも可能だが、検査結果がでるには時間がかかるために、検索開始と同時に抗菌薬投与を開始したり、起因菌検索をしないまま、増悪予防のために、盲目的に投与を開始することもある。
また効果判定も菌の静菌や殺菌を確認することも少なく、解熱や全身状態の改善をもって治療終了とすることが多いのが実態である。
以上によって在宅での抗菌薬使用の現状をまとめると
1・個々の医療者の判断で、細菌感染の可能性が高いもしくは心配されると考えられる場合、起因菌の検索をしつつ、経口、径静脈などの抗菌薬投与が行われている。
2・抗菌薬の選択は、患者の状況や介護状況、医療者の訪問頻度や滞在時間の関係などにより、
3・効果判定は採血結果による炎症反応の改善や全身状態の改善をもって行われることが多い。
のが、実情といえる。
さて、昨日当院で以前から非常勤でご勤務下さっている東京医大病院 感染症科 感染制御部の下稲葉みどり先生に「在宅における抗菌薬適正使用は可能か?」と題して、在宅での抗生剤使用の在り方についてご講演をいただいた。
先述のように、在宅での抗菌薬使用の仕方は病院、特に大学病院での抗菌薬使用の原則からは大きく外れているのが実情である。
その理由は、医療現場の違い、患者状況の違い、医療目標の違いなどが大きい。
しかしその中でも、適切な抗菌薬使用をどのようにすべきか、系統的にお話しいただいた。
先生のご講演内容を私なりに理解したところでは、
在宅医療の現場で多用されているセフトリアキソン(ロセフィン)は第三世代セフェムで広域の抗菌作用、腎機能に依らないことや半減期が長いことで、在宅では使用しやすいのが実情だが、胆石、急性化膿性胆管炎などの合併症に注意がいる。
セフトリアキソンが効きづらい菌による発病の可能性が高い蜂窩織炎、腸炎、カテーテル感染症などでは、それぞれミノマイシンやバンコマイシン、マキシビームなど他の抗菌薬の使用を検討すべき。
またセフトリアキソンが多用されている肺炎、誤嚥性肺炎、尿路感染などでは、それぞれクラビットやジスロマック、ユナシン、クラビットなどの単剤使用や併用を検討する。
感染症に対する解熱剤使用は、感染を増悪させる有意差を持たないので、その間の体力低下を防ぐ意味もあり、適切な併用が望ましい。
とのことでした。(上記は下稲葉先生のご講演内容から、あくまでも英個人が理解した内容と考え、演者の講演内容とは別個のものと理解ください)
最後に、在宅における感染症診療のまとめとして、
「総じて、対症療法で解熱が得られれば、いわゆる病院的な培養検査、厳密な抗菌薬選択は不要なのでは。熱が下がって意識が戻る。ご飯が食べられることが大事。」
というお話は、まったくもって実際的なお話であり、大変示唆に富む内容だったと感じ入りました。