冬至も近くなり、日の出が遅くなっている。6時過ぎまで暗いことが多くなった。
カーテンを開けたままで寝る私は、朝日の明るさに起こされることを習慣としている。
これまでは、早すぎた目覚めが、遅れている。毎週月、水、金、7時半開始の早朝勉強会に間に合わなくなりそうなぐらい、目覚めが遅くなってしまうこともある。
もともと目覚まし時計を持たなず、自然に頼っていた私にとって死活問題だ。
「春眠暁を覚えず」ならぬ「冬眠暁に起こされず」。といったところか?
在宅医療・訪問診療・外来診療|東京都新宿区|新宿ヒロクリニック
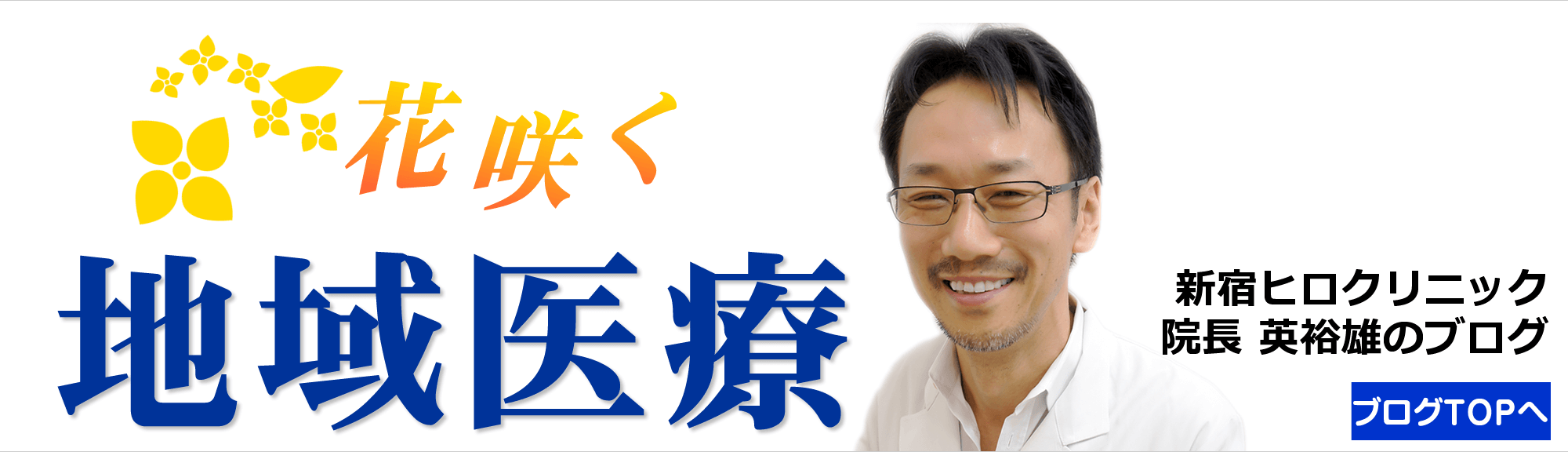
冬至も近くなり、日の出が遅くなっている。6時過ぎまで暗いことが多くなった。
カーテンを開けたままで寝る私は、朝日の明るさに起こされることを習慣としている。
これまでは、早すぎた目覚めが、遅れている。毎週月、水、金、7時半開始の早朝勉強会に間に合わなくなりそうなぐらい、目覚めが遅くなってしまうこともある。
もともと目覚まし時計を持たなず、自然に頼っていた私にとって死活問題だ。
「春眠暁を覚えず」ならぬ「冬眠暁に起こされず」。といったところか?
元気な人には近い距離でも、足腰の弱っている人にはとてつもなく遠い距離となる場合がある。
歩いて15分程度の距離だが、当院にはバスで来なければならない患者さん。バス停まで一人では歩けないから、通院には同行者の付き添いが必要だという。でも当院の言語リハビリを利用したいというのが希望だった。
3か月に一度程度の、病院通院は別居の親族が来て送ってくれるという。しかしリハビリのためにコンスタントに当院に通院するのに、その都度遠く離れて住んでいる親族を呼び出すことはできない。訪問リハという手立てがあるが、介護保険はヘルパー利用で一杯になっているという。
「当院から送迎に来させましょう。」私の提案に「そんなことお願いしていいんですか?」顔をほころばせながらも、申し訳なさそうにしている。
「もちろんです。週に1~2回来てください。今が大事な時期ですから、しっかりリハビリしてください。」私はちょっと自慢気に、太鼓判を押した。
当院では、これから往診車などを活用しながら、無料送迎サービスを始めることとしている。
これまでも不定期では、何人かの患者さんに利用してもらってきた。
今後は少しずつ定期的な利用も受け付けていきたい。
そんなことが言えるのも、送迎してくれるスタッフがいてくれて、さらに外来でしっかり患者さんを受け入れ支えてくれるからだ。
ありがたいことである。
外来の事務が新生しました。
これまで4人が固まって仕事していましたが、患者様担当。診療担当。に分かれて2人受付会計、医事事務を分担することになりました。
最後にみなさんの感想を聞きましたが、いい感触を皆さんが持っていることに安堵しました。
この2日間、私は地区医師会の指示で認知症サポート医研修会に出席していた。
認知症サポート医とは、地域のかかりつけ医が認知症患者さんを診療しやすく、基盤整備したり、地域の困難事例に対応する医師である。
国は超高齢化のスピードに合わせて、認知症初期集中支援チームを作り、認知症地域支援推進員を配置するという。それをサポートするのが認知症サポート医の役割でもある。
全国から340名の医師が参加する研修会は土曜日の午後から日曜日の昼過ぎまで、トータル10時間以上の研修だったが、今後の役割の大きさに比べれば、決して長い研修ではない。
しかし実は、これまで各地の現場でそれなりに普通にしてきたことだ。このように制度やシステムができると、何かこれまでも普通にしてきたことが、特別な意味や役割を持つようになる。
あえてそういう意味や役割を作り、制度化なければならないことに、時代の焦りを感じる。
今後たった数十年で社会の人口構成が逆転する。 いかに高齢期の様々なステージを無理なく過ごせるようにするかを急速に整備する必要がある
中でも認知症施策は喫緊の課題だ。何が何でも急いで体制を作る必要がある。
そんな意図がまざまざと感じられる研修会だった。