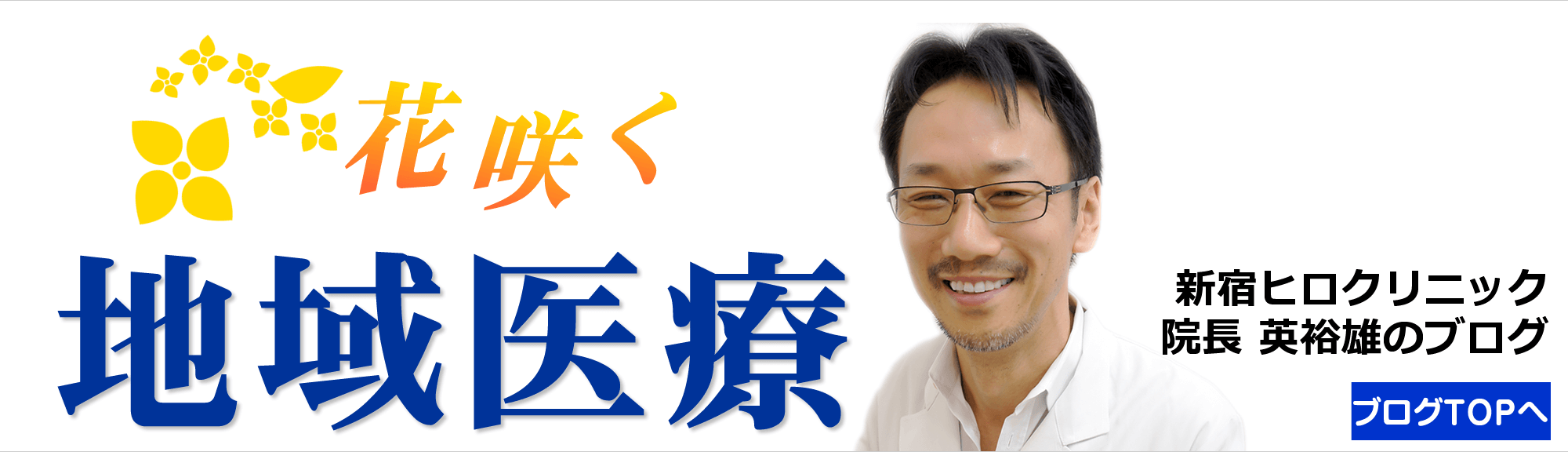示唆をすることもできる。サポートすることもできる。しかし・・・どう生きたいかは自ら決めるしかない。
日曜日の夜に電話が鳴る。
入院中の、普段見ていない患者さん。時々必要時に往診していた患者さんが、経口摂取困難と言われ胃瘻の増設をすべきかどうか迷っているという。
胃瘻をつけても自宅で過ごすことは十分可能だし、胃瘻をつけずに自然に自宅で過ごすことも可能だ。どう過ごしたいかさえ明確にしてくれれば、アドバイスもできる。
しかしどう過ごしたいかを明確してくれればいくらでもアドバイスできる。
それも困難なようだ。それもわかるような気がする。 ならば少しゆっくり話あったほうがいいと思う。だから、明日の私の外来に来ていただければ、いろいろご相談に乗れるとお伝えする。
しかし、明日は仕事だから、無理だという。
地域には、答えのない話もある。