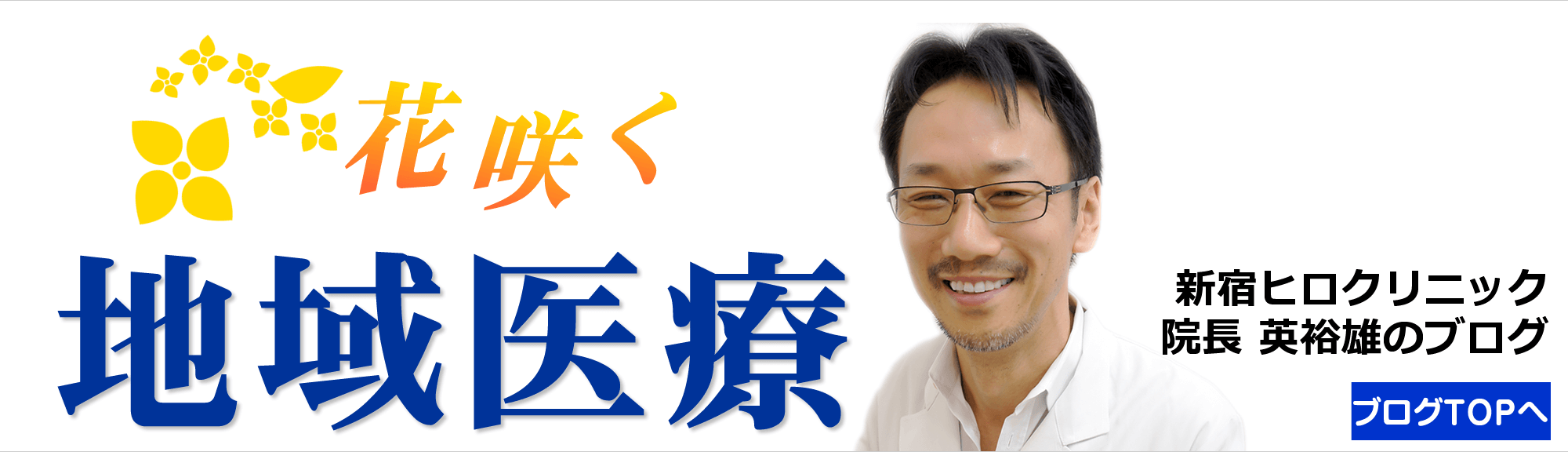普段から多くの患者さんの検診や健康指導をしているにもかかわらず、自分では億劫で、検診を受けていないという医者は少なくない。
私も、自分から率先して受けることはない。しかし、自分の人生の節目を占ったりするときには、自ら人間ドックに入ったりする。
数年に一度は、そういう節目を迎える。前回は3年前、その前はさらに4年前だった。たいていは人生の悩ましい時期だ。今死んではいけない。今からしばらくは頑張らなければならないと思うとき、私は検診を受けているのだ。
最初の時には、何も異常はなかった。
前回では、少し異常が見つかり。
今回は紹介状までもらう羽目になった。
しかしまだ高をくくっている自分がいる。
「この年になれば、少しの異常ぐらいあって当たり前・・・」どうせ受診したって、結論だってわかっているし、受診するだけの時間ももったいない。
そんな言い訳をしている自分がいる。
私はだらしない患者さんを叱らない。なぜなら自分が一番だらしない患者だからだ。