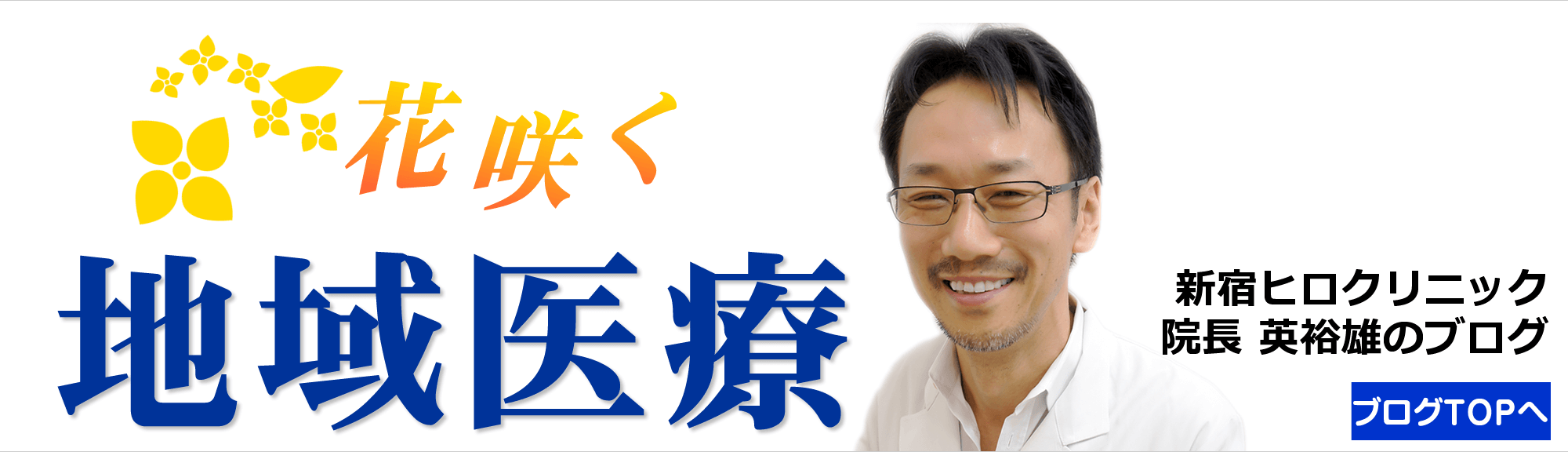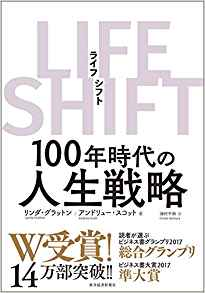世界に先駆けて日本では高齢化が進んでいることは周知の事実である。そして今や100歳以上まで長生きすることも珍しくはなくなりつつある。
実際当院でも、最近100歳以上の患者さんが増えている。今後はさらに100歳以上まで長生きする人が増えることも予想されている。
それは決して他人ごとではなく、私たちも100歳以上になるかもしれない。
ましてや子供たちの時代には・・・
しかし実際、これだけの長命を生ききるための戦略を、明確に持っている人はいないのではないだろうか?
「LIFE SHIFT 100年時代の人生戦略」という本に出合った。
本書は、これまでの人生モデルとは全く異なる人生100年時代の人生モデルを明確に提示している。その理由とともに・・・
すぐに消化し、実行できる人は少ないかもしれない。しかし本書が語っていることが真実であると感じる。
自分たちが、今そして将来を、どう生きなければならないか?
痛切に考えさせられる問題の書である。
惜しむらくは、本書が日本人によって書かれなかったことである。