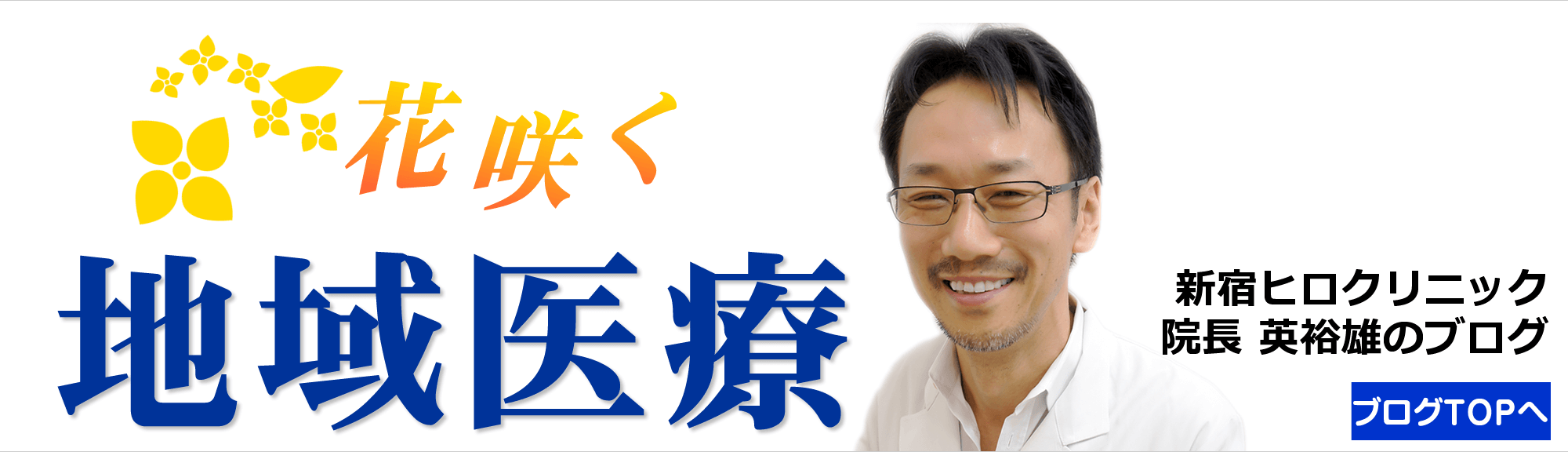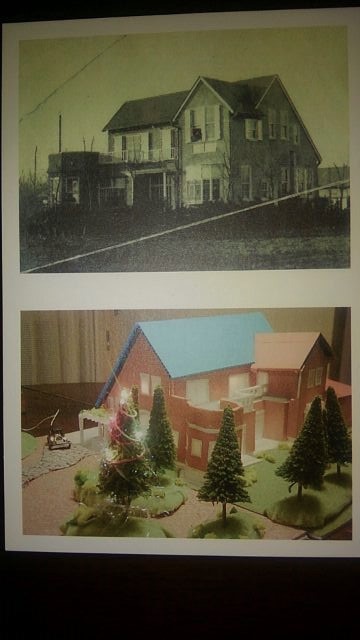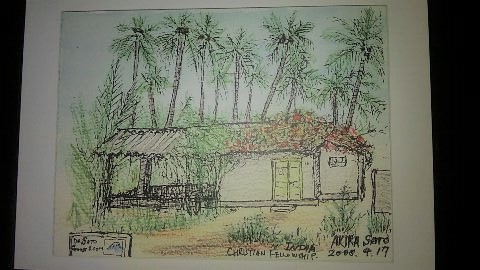昨日私は東京都庁で開かれた「第15回東京都輸血療法研究会」に出席した。
輸血療法を取り巻く最新の話題に触れながら、昨年作成された小規模医療機関における輸血マニュアルについて、在宅医療側からの検証的意見を述べさせていただいた。
実際小規模医療機関での輸血の仕方は、さまざまなバリエーションがあるようだ。それは医療機関の事情、患者さんの事情など様々な事情の違いによるものであり、すべてガイドラインやマニュアル通りにはいっていないのが実情である。
こうした専門家が集まり、英知を結集してできたガイドラインを前に、感じたことを改めて整理してみた。
:::::::::::::::::::::::::::
元来在宅医療は、医学的厳密性を目指すのではなく、患者さん、ご家族の療養生活の円滑性や療養生活の意義の向上を目指すものである。したがって、たとえば貧血が全く見られないにもかかわらず、輸血をしてもらわないと生活が不安で、不安で仕方ないという人に対しては、輸血を前向きに検討しなければならないこともあるし、高度な貧血があったとしても寝たきりで、貧血による苦痛がないところで、あえて輸血のために針を刺したりすることを躊躇することもある。つまり輸血の適応は、貧血の有無が指標だけではなく、むしろその人にとってのいかなる療養の正当性を求めるか、こそが輸血の適応の判断基準となるのだ。
当院には、入れ代わり立ち代わりだが、現在30名以上の東大医学部の学生が実習に来ている。彼らに決まって言うことがある。
「君たちは東大の医療が一番だと思っているかもしれないが、医療の正当性はその場その場によって異なる。たとえば特別養護老人ホームに入所している人に東大の医療を適応すれば、大きな迷惑になるだろう。一方で東大に入院している患者さんに特別養護老人ホームの医療を適応すれば、ふざけるなと怒られるに違いない。医療者は、それぞれの現場や、相手によって、TPOをわきまえることが重要である。」ということである。
例えば燕尾服は、イギリスの宮殿での正装かもしれないが、ハワイやアフリカではむしろ暑苦しいだけの、無理な正装で、むしろ滑稽でさえあるように、ガイドラインもある現場には適正であっても、ほかの現場に常に適正であるとは言えないのだ。
もしガイドラインが、医学的厳密性を求めるものだとしたら、在宅医療の現場ではいつまでたっても使い物にならない。個々の患者の療養や人生の正当性を目指すためのガイドラインでなければ、在宅医療の現場では使い物にならないのである。
::::::::::::::::::::
私はガイドラインが不要だとは思わない。しかしガイドラインだけで医療ができるとも思っていない。医療現場の違い、患者さんの状況による違い、それらを加味したガイドライづくりこそがいま望まれていると感じている。