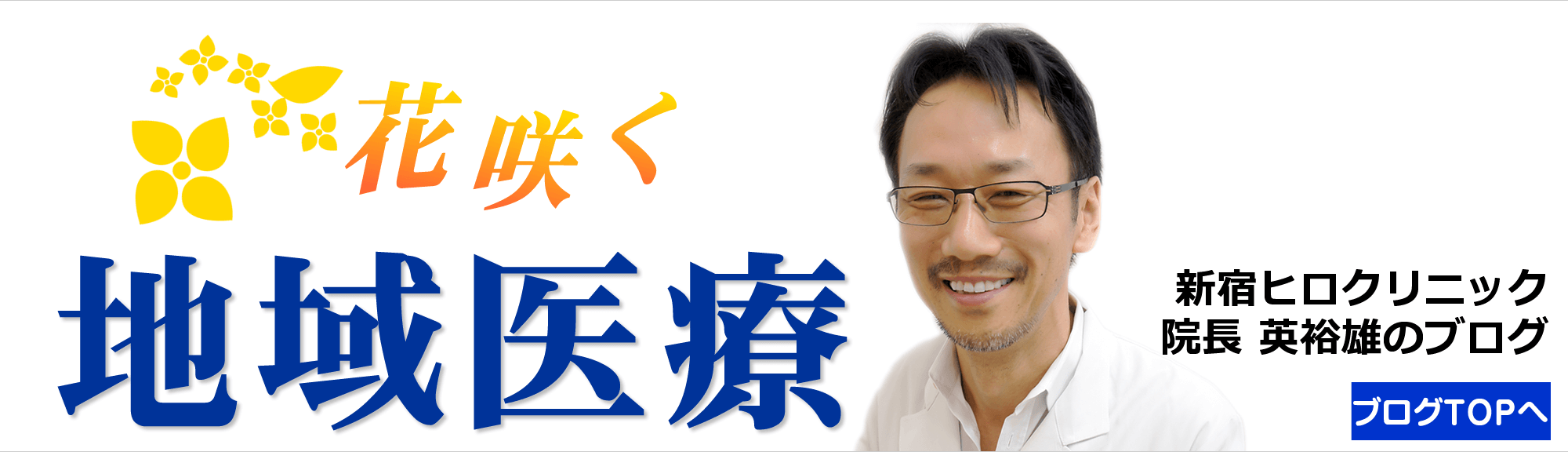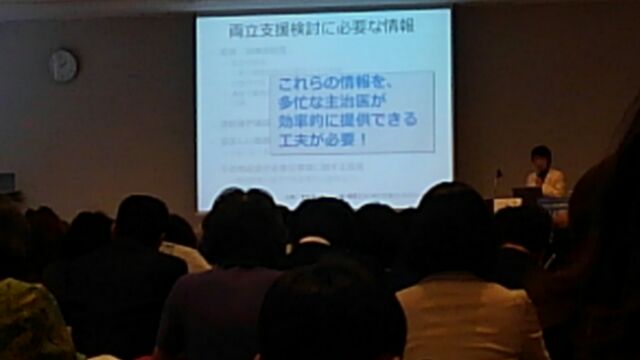日本の在宅医療の礎を築き、のちに日本在宅医学会を創設された佐藤智先生が、常々若手の在宅医たちにいっていた言葉がある。それは、「病気は家で治すもの.」という言葉だった。私もその薫陶を受けた一人であることを今も誇りに思っている。
:::::::::::::::
私が在宅医療を始めたのは、今から20年前だった。当時は、訪問診療をする医師も少なく、今のように在宅医療専門の医療機関などもない時代だった。どちらかというと救貧的、人道支援的在宅医療が中心だった。
当時、わたしは日野原重明先生と一緒に患者さんの在宅医療を担当したことがある。聖路加国際病院の院長だった日野原先生は、すでに80歳を優に過ぎていたが、昼間の診療や夜の様々な公務を務めらえた後に、毎晩数人の患者さんの往診することが常だった。患者さんのところに行くのは、夜の9時を過ぎていることも珍しくなかった。日中の病状管理は私のほうでおこない、夜に日野原先生が顔を出して、励ますという形の併診が多かった。そういう患者さんのひとりが、ある時誤嚥性肺炎を併発して、聖路加病院に入院になった。ご高齢(といっても、日野原先生より若かったが・・・)の方で、しかも虚弱な方だった。すぐに日野原先生が入院を手配してくれて、スムーズに入院することができた。
入院して数日後、病室に見舞いに行って、患者さんを一目見た日野原先生は、主治医に「ここにこのまま置いておいたら、死んでしまう。すぐに退院して自宅に返しなさい。」といったという。
それを聞いた主治医はとてもたまげた。まだ抗生剤治療を始めたばかり、血液データも改善していない。そんな状態で自宅に返せなんて、なんて無謀なんだと仰天した。しかし院長の命令だから、従わなければならない。困り切った主治医が私に相談するために電話してきた。「うちの日野原が無体なことを言っていますが、先生どうしましょうか?」と困り果てていた。
「家でも抗生剤治療を継続できます。先生がはじめられた治療を家でも続けられますので、ご安心ください。」と私が答えると、主治医の先生は安堵したようで、さっそく患者さんは退院することとなった。
退院された後、日野原先生と私は往診を繰り返した。私が日中の抗生剤治療を行い、夜は日野原先生が往診する。入院中は、食事や水分摂取もせずに点滴だけでベットの中に横たわっていた患者さんに向かって、日野原先生が励ます。なるべく座って過ごす。少しずつ食べれるものを食べて、動くことも並行するようにと指導された。
治療も大事だが、それ以上に生活を維持することが重要だと日野原先生は言いたかったのだろう。そのかいもあって患者さんはみるみる回復していった。
高齢者医療において、いたずらに入院医療を長引かせることの弊害が叫ばれ始めたのは、つい最近のことだ。当時はまだ病院で保護的に高齢者に医療を行っていくことが主流の時代だった。当時から、医療界の先駆者として活躍されていた日野原先生だったが、実は誰よりも優れた在宅主治医だったのだ。
:::::::::::::::::
まさに先人たちが実践していた在宅医療とは、「病気は家で治すもの。」だったのだ。