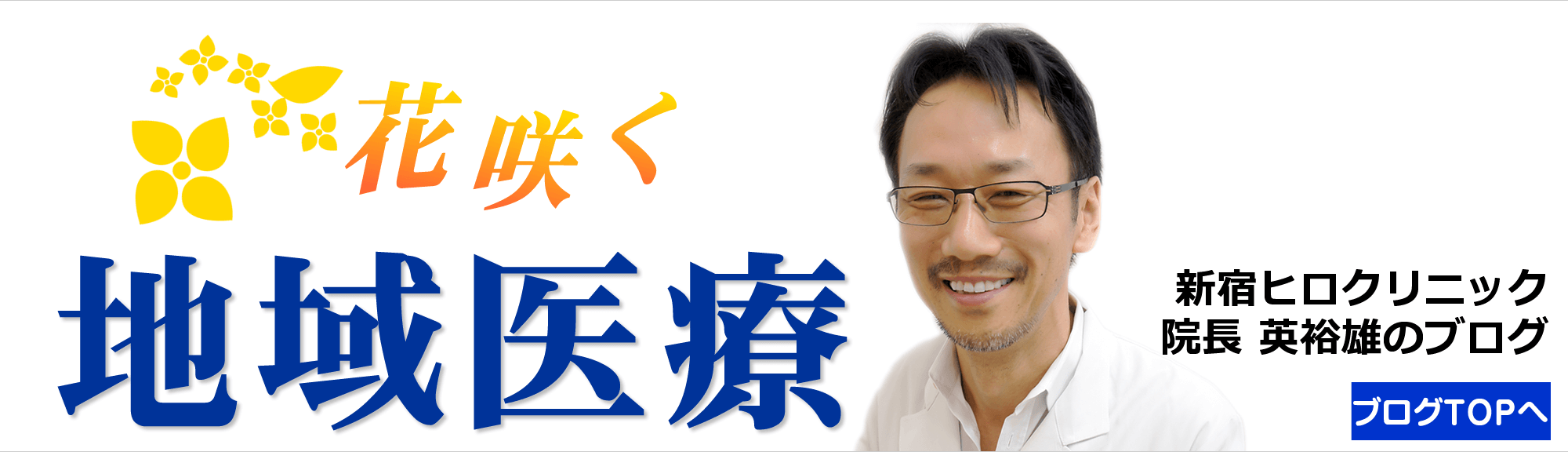本日私は向山先生と、日本橋で開かれた第4回がんサポーティブケア研究会に出席した。がんサポーティブケアとは聞きなれない言葉だが、私たちも今まさにがんの在宅医療からがん全体のサポーティブケアの在り方について思いを巡らしているので、大変関心がある研究会だった。癌研や聖路加、がんセンターなどがん医療に携わる様々な医療者が集まり、がん治療中の症状コントロールを含めて、がん患者が直面する問題を討議する会だった。
そしてそこで昨今創設されたばかりの「日本がんサポーティブケア学会」の田村和夫会長の講演を聞く機会を得た。
講演の中で、田村会長が話す。「がん患者の80%は60歳以上であり、がんで亡くなる患者さんの80%以上が65歳以上である。」と。
今の60歳や65歳はとても元気だ。だから高齢者だからといっても必ずしも虚弱ではない。しかし確かにがんを患っているが、全身状態の低下はパーキンソン病によるという患者さんもいる。入院してがん治療を受けるのはいいが、その間に認知症などの障害が進んでしまう患者さんも少なくない。
今後がんの患者さんの支援は単に治療ではとどまらない。生活支援、介護、環境整備など様々な支援が必要である。
がんサポーティブケアという新しい概念を私たちは今模索し始めている。