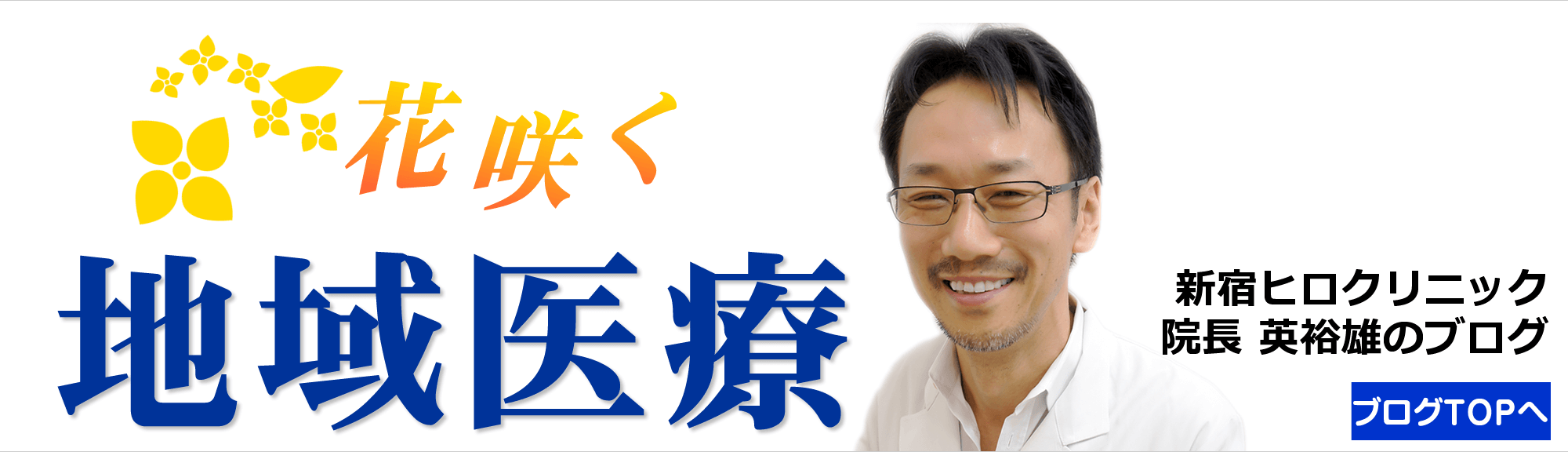在宅医療・訪問診療だけをしていた時には気が付きませんでしたが、8年前から外来を初めてわかったことがあります。
訪問診療を受けている患者さんに比べて、本来は元気なはずの外来にいらしてくださっている高齢者の方のほうが突然変化される方が多いように思います。
訪問診療が入っている方は、診療だけではなく様々な介護サービスが自宅に入っているので、何か変化があった時周囲の方がすぐに気づいてくれます。しかし外来にいらしている方はあまりサービスを使っていない方が多く、何か変化が起こってもだれも気が付かない。よほど大きな変化になって初めて周囲が対応するということが少なくないのです。
真夏の熱中症で急変する方は、訪問診療の患者さんでは少ないですが、軽度の認知機能低下など生活機能低下がありながらも、そこそこ一人暮らしで来ているような方が非常に多いのです。高齢者医療においては、起こったことに対応する医療だけではなく、起こりそうなことを未然に防ぐ医療が必要だと気付かされます。
少し下肢筋力の衰えを感じている方には、転倒予防を。痰がらみが多くなっているとい方には、誤嚥予防を。全体に虚弱化が進んでいる方には、介護サービス導入を。
要支援や要介護認定をもらていても、まだ困っていないから、介護サービスやリハビリなどは使っていないという方が非常に多いですが、転ばぬ先の杖のような高齢者医療ケア体制が必要に思うのです。