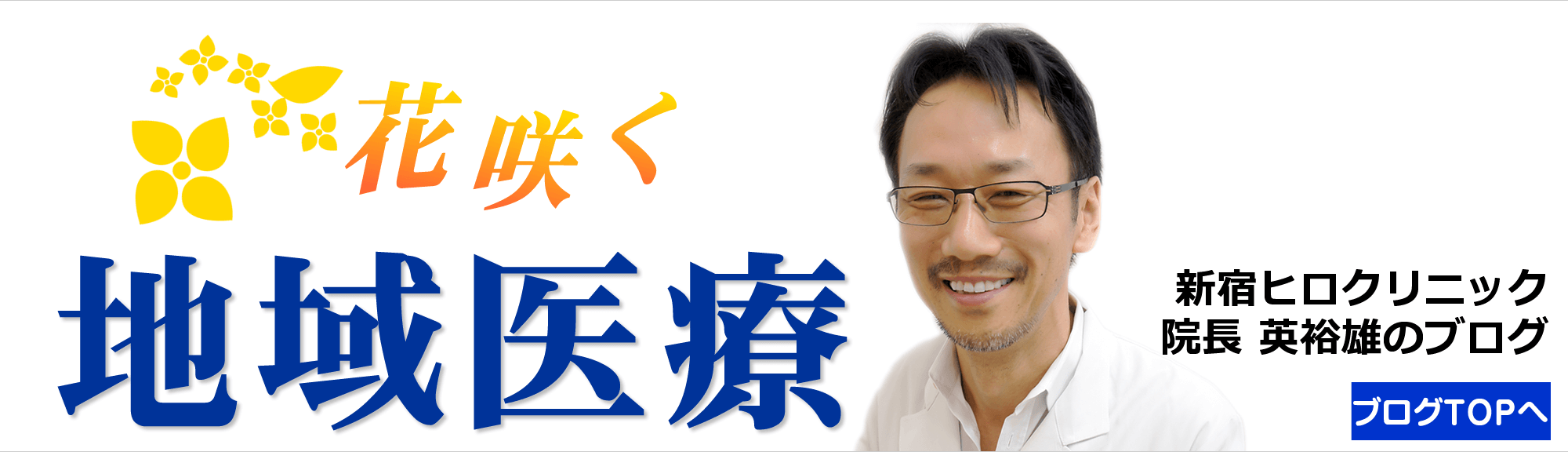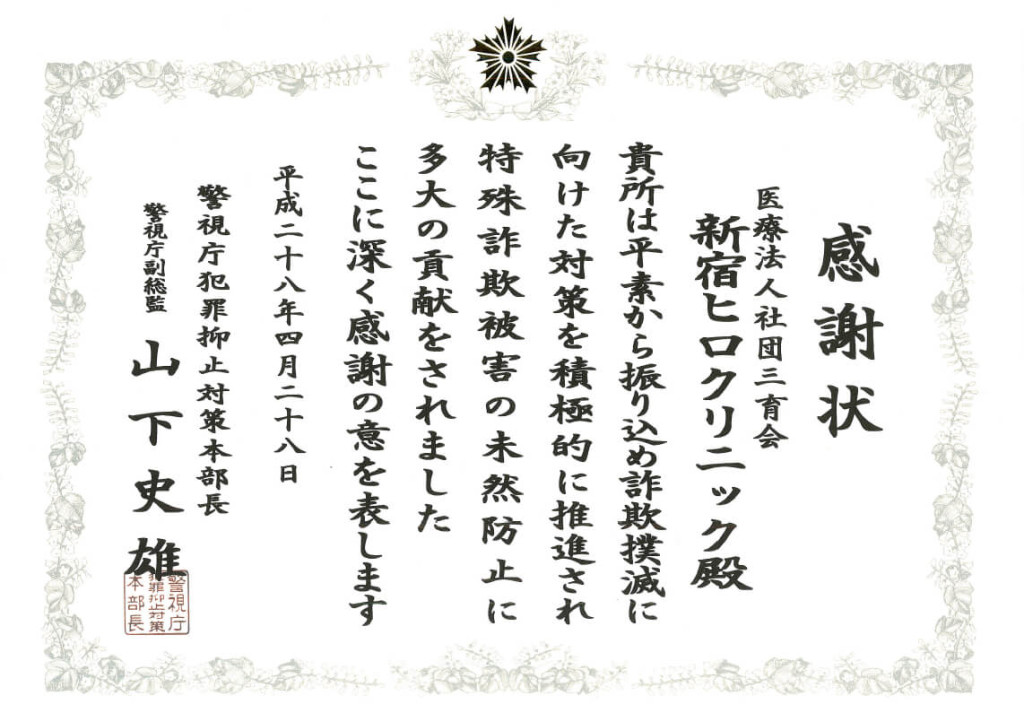医学や医療の在り方もその時の時代ニーズによって大きく左右される。
かつて多くの小児が、感染症や様々な事故などの急性疾患で命を落としていた時代は、感染症や小児疾患に対する医療の充実が喫緊の課題だった。しかし幸い、様々な社会努力により、これらが徐々に解決され、小児疾患が少なくなってくると、その後、結核やがん、生活習慣病などへの疾患対応が大きな課題として取り上げられるようになった。
昨今は高齢者の増加を迎え、認知症や骨粗しょう症などの高齢疾患への対応が急がれている。
しかし、いくら高齢疾患の時代になったとしても、小児疾患や成人疾患の重要性はなくならない。むしろそれぞれの疾患が違った課題を呈するようになっている。
例えば水ぼうそうは小児の代表的ウイルス感染症だったが、最近はワクチンの普及により、水ぼうそうを発症する小児は激減している。そのおかげで、水ぼうそう患者に触れることがなくなったので、成人の水ぼうそうの免疫力が低下しているというのだ。小児の時に水ぼうそうを患ったことのある人の体内には、水ぼうそうのウイルスが潜んでいる。それが免疫力によって抑えられている。その免疫力が低下していくと、潜んでいたウイルスが暴れだす。つまり高齢者になるとさらに免疫力が下がっていくことで、帯状疱疹という別の病気の形になって発症しやすくなっているのだ。最近では、水ぼうそうに触れなくなった成人や高齢者の帯状疱疹の発症が急激に増加している。
このように同じウイルスでも、かつては小児で問題だった感染症が、小児では問題にならなくなり、高齢者で問題になるなど、その時の時代状況によって異なった課題を医療界に突き付けている。
また糖尿病なども成人にとっては、失明や、腎不全、足などの壊疽の原因になりえる非常に怖い病気だが、高齢者にとってはこれらの合併症はもとより、認知症や骨粗しょう症を進めやすくなるといわれている。今後は糖尿病のコントロール目標も変わっていくことが予想される。
糖尿病だけではない。様々な疾患がそうである。さらに新しい治療や診断方法も日進月歩に進歩している。いくら勉強会や、研修会に出席しても、様々な本や文献を読んでいても、これらすべてについていていくことができなくなっている。そういう時代には、ガイドラインというものがもてはやされる。
多くの学会がその時々の病気のマネージメントの仕方をマニュアル化して、わかりやすく簡潔にまとめる形でガイドラインの普及を図っている。そういうガイドライン通りの医療を行っていくことで、これら時代の状況にマッチしていく必要があるというのだ。
しかしガイドラインも万能ではない。新しい病気に対する新しい治療などがガイドラインに乗るには時間がかかるからだ。いまわたしたちガイドラインを参考にしつつ、新しい知見を補充していく努力が不可欠な時代になっているのだ。